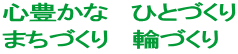【第6話】
『お姫さまが、泣いて坂をくだる』
(新しいウィンドウで開いています。)
難攻不落を誇った金鑵城もついに落城の時を迎えました。
広間に集まった武士たちは、城主を囲んで最後の酒を酌み交わしておりました。広間の片隅に幼い姫がこっくり、こっくりと今にも倒れそうに居眠りをしています。一人の侍が、「殿、幼き姫を道連れにするのは不憫です。なんとか城からお逃がしすることはできないでしょうか。」 城主は、「もし敵に見つかっても、幼い女子では無茶はしまい。」と、夜の闇に紛れて逃がすことにしました。「なんとか逃げのび、わしやこの者たちの後生をとむらってくれ、たのむぞ。」と、姫に告げました。すぐに、姫は着物を着替え城を出ました。暗い闇の中、怖さ、心細さ、そして別れの悲しみから、坂を下る途中、大粒の涙が止まらなかったとのことです。これ以後、姫の下りた坂は「泣き坂」と呼ばれるようになりました。
さて、民家までどうにかたどりついた姫は、「開けて下され、助けて下され。」と、民家の戸を激しく叩きました。次の家、その次の家へと行っても返答がありません。みんな逃げてしまっていたのです。姫は、どうしていいかわからず、ただ座り込んで、地を摺(す)るようにもだえ、泣き叫びました。このことから井摺(いすり)という地名がついたとされています。
夜空が急に赤くなりました。姫がびっくりしてその方向を見上げてみると、なんと金鑵城が燃えているではありませんか。「お城が、お城が燃えておる。」力の尽きた姫は、敵兵の手にかかるよりはと、近くにあった深い池に身を投げ、命を絶ってしまいました。以後、この池に人が近づくと火の玉が現れ、それを見た人は気を失ってしまったとのことです。人々は、お姫さまの祟りだと言い、この池を「火の壷」と呼ぶようになりました。